損切りしない株式投資、何が問題?
株式投資を始めたばかりの方の中には、「損切りはしたくない」「いつか株価が戻るはずだから待とう」と考える人が多いかもしれません。しかし、損切りをしない投資には大きなリスクがあります。この記事では、損切りしない投資がもたらす問題点と、それを避けるためのポイントを解説します。
1. 損切りしないことで失う「お金」と「時間」
損切りをしない最大の問題は、お金と時間を無駄にしてしまうことです。損失を抱えたまま放置すると、その資金を他の成長可能性のある投資に回すことができなくなります。
例えば、A株を1,000円で買い、現在の株価が500円まで下がったとします。この株が回復するのを待ち続ける間に、別のB株が同じ1,000円の投資で大きな成長を遂げる可能性を見逃すかもしれません。
2. 「塩漬け株」が資産形成を妨げる
損切りをしないと、「塩漬け株」と呼ばれる状態になることがあります。これは、株価が下がりすぎて売れない状態を指します。このような株を持ち続けると、ポートフォリオ全体のパフォーマンスが悪化するだけでなく、投資判断が偏ってしまいます。
塩漬け株の例:
- 過去に人気だったが、現在は競争に敗れ業績が悪化している企業
- 事業の将来性が乏しく、配当も低いままの企業
3. 株価ではなく「企業価値」に注目する重要性
損切りをためらう理由の一つに、「株価がいつか戻るかもしれない」という希望的観測があります。しかし、株価が下がる根本的な原因は、企業価値の低下にあります。企業価値が右肩下がりである場合、いくら待っても株価が元に戻る可能性は低いです。
企業価値が下がる原因の例:
- 業界全体の衰退(例:フィルムカメラ業界)
- 経営の失敗(例:財務体質の悪化や市場シェアの喪失)
このような場合は、早めに損切りをして資金を他の成長企業に振り向ける方が合理的です。
4. 損切りのタイミングを決める方法
損切りをためらわないためには、事前に明確なルールを設定することが重要です。
損切りルールの例:
- 購入時に損切りラインを設定する:例えば、購入価格から20%下落したら売る。
- 業績悪化をチェックする:売上や利益が2期連続で大きく減少した場合に売る。
- 自分の判断を疑う:感情に左右されず、客観的なデータに基づいて判断する。
5. 損切りで成功する投資の実例
プロの投資家でも損切りは日常的に行われています。例えば、ウォーレン・バフェットはかつて航空会社の株を保有していましたが、業界の長期的な成長性に疑問を感じ、コロナ禍で大幅に損切りをしました。この決断により、彼は損失を最小限に抑え、その資金をより有望な投資先に振り向けることができました。
まとめ:損切りは「次の一手」へのパスポート
損切りは「失敗」ではなく、「次の成功への準備」です。企業価値が右肩上がりでない株を持ち続けても、時間とお金が無駄になる可能性が高いです。大切なのは、感情に左右されずに損切りを実行し、その資金を将来性のある企業に再投資することです。
損切りを正しく行い、効率的な資産運用を目指しましょう!

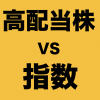

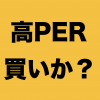




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません